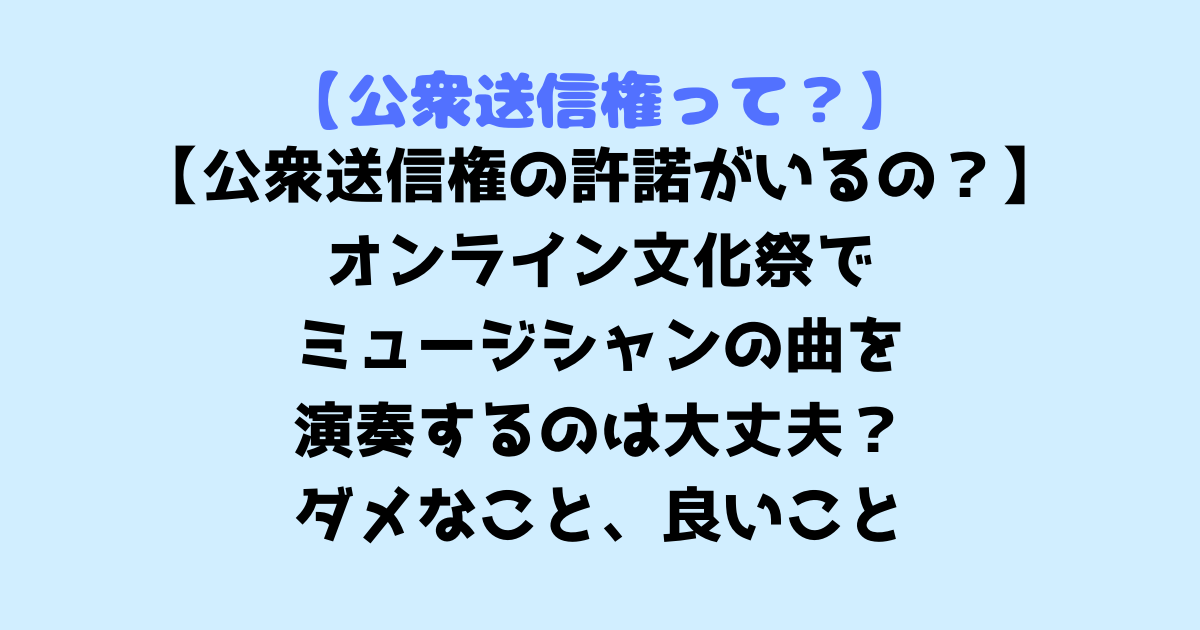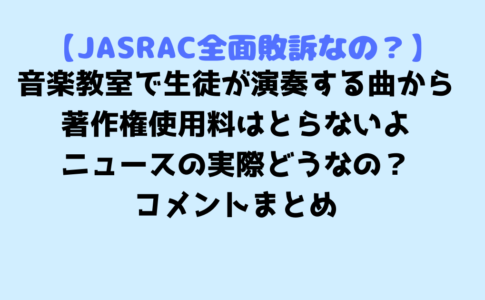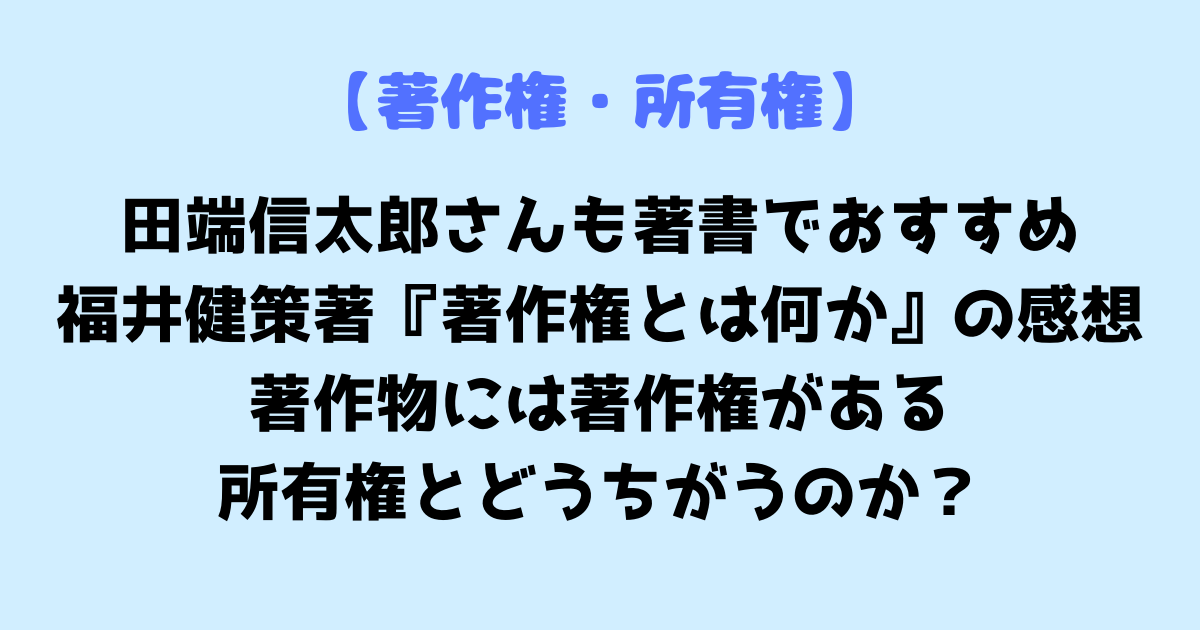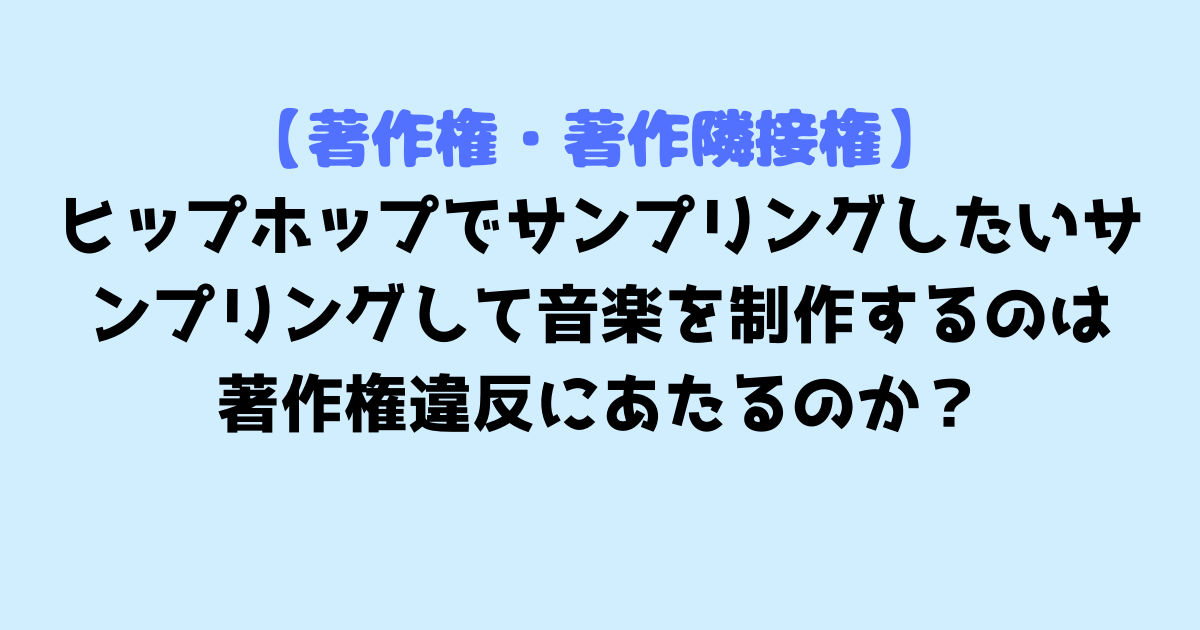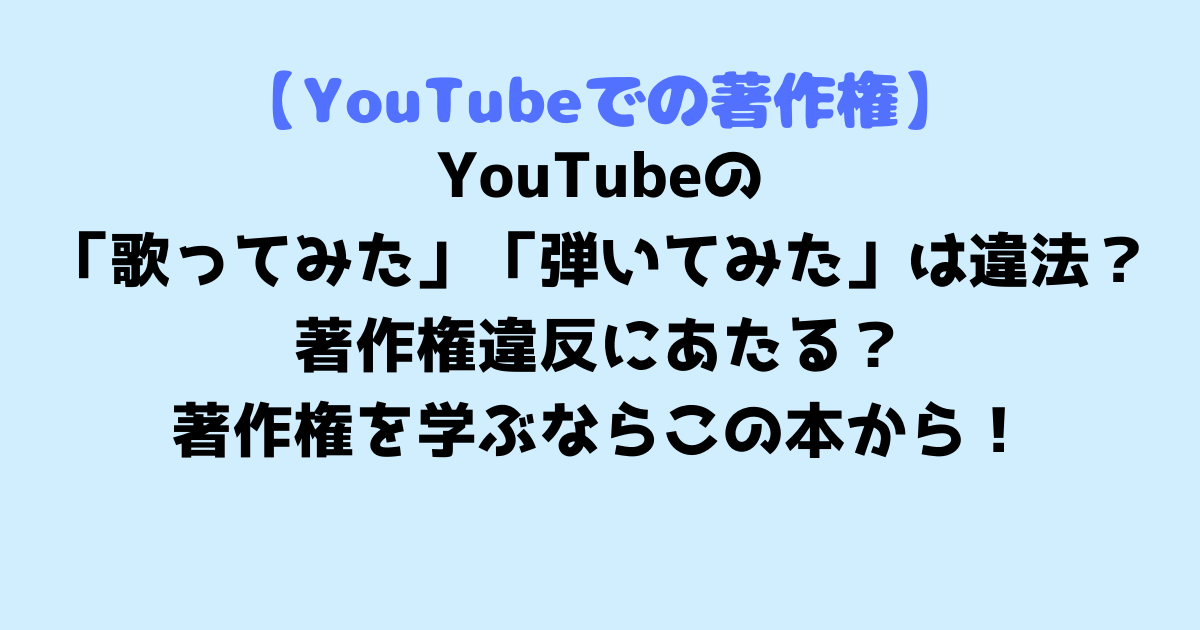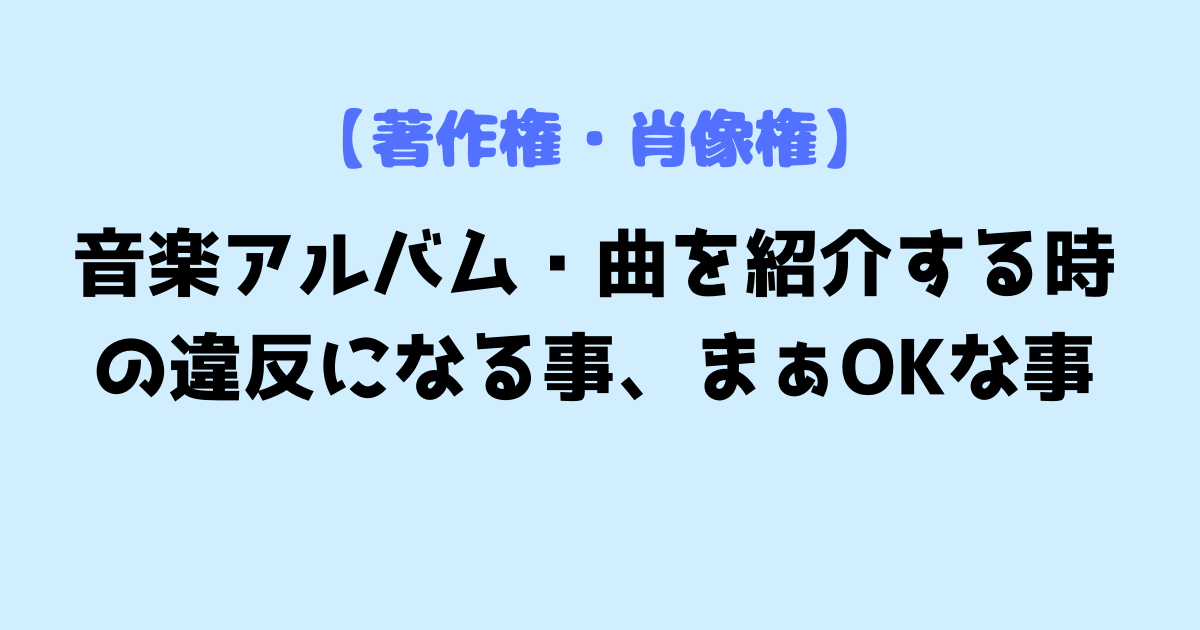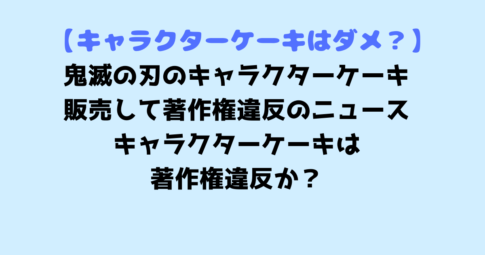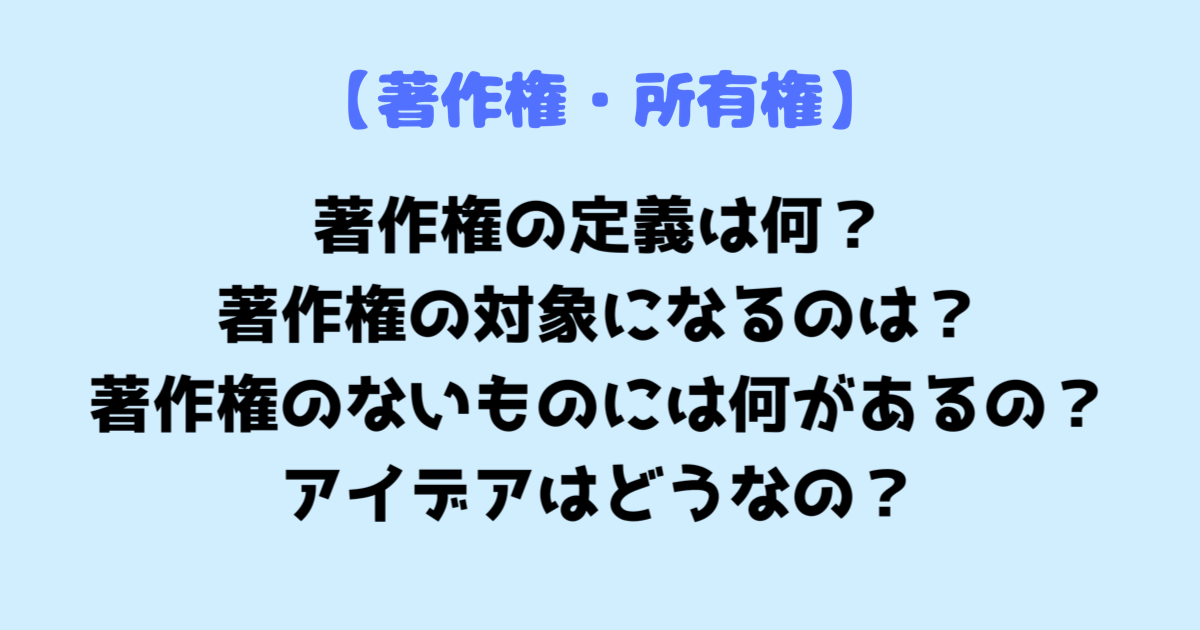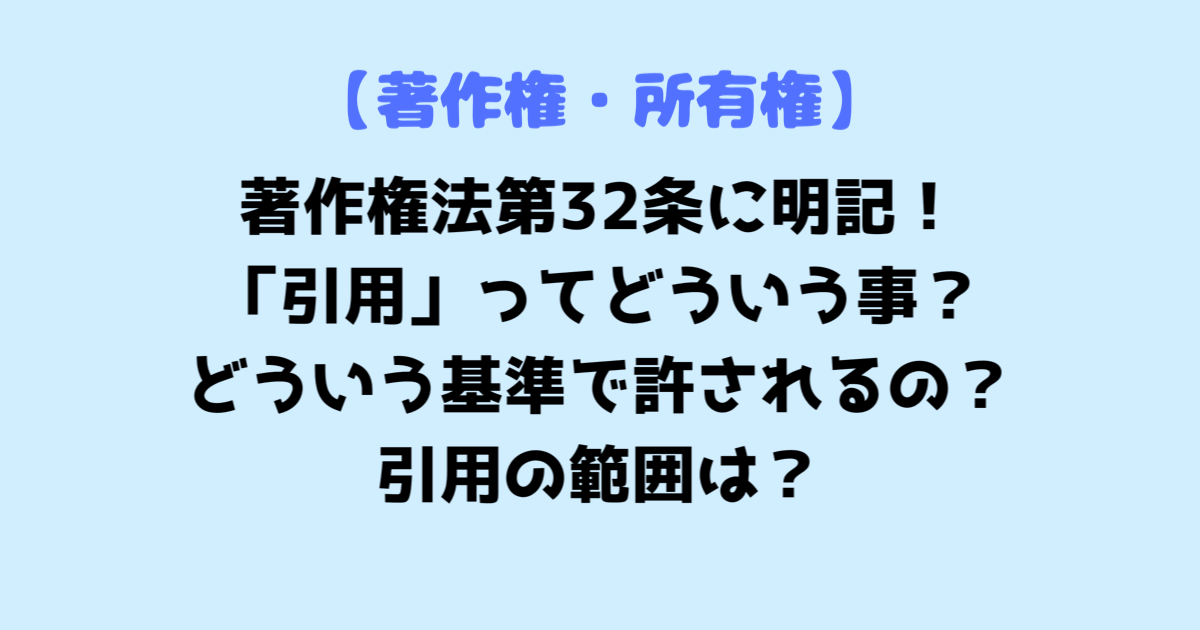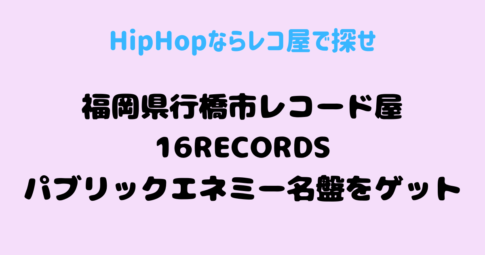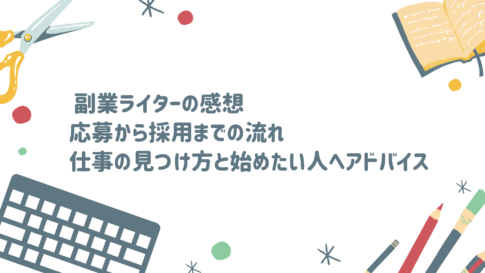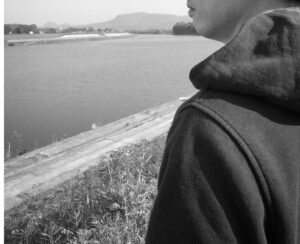オンライン文化祭は著作権を侵害するの?
コロナ禍において、気になるニュースがありました。以下ブログはこのニュースを引用しています。
[blogcard url=”https://news.yahoo.co.jp/articles/5b48fb874671d35c3853ac251ba3007a9c9ec439″]ニュースを読んで、結論から言います。
オンライン文化祭でミュージシャンの楽曲を演奏しても著作権を侵害していることにはなりません。
オンライン文化祭は著作権侵害にならない
著作権侵害にあたるのは、基本的に金銭が発生することだと言えます。原則として以下のことを守っていれば、著作権侵害にはあたりません。
- 営利を目的としないこと
- 聴衆または観衆から料金を受けないこと
- 実演家に報酬が支払われないこと ※ニュースより引用
文化祭で学生を中心とした人たちが、楽しく音楽を楽しんだり、その姿を広く知ってもらおうとするところには、営利な目的などなく、JASRAC的にも著作権を侵害していない、との見解を示しています。
公衆送信権の許諾は必要か?
文化祭でミュージシャンたちの楽曲を楽しく演奏することは、営利目的でないこと、演奏者に報酬が支払われないことなどがあげられ、著作権侵害にはなりません。
演奏することはOKってわかった。じゃあインターネットで放送することは問題ないのか?
インターネットでほかの人が作ったものを流そうとすると、「公衆送信権」の許諾を得る必要があります。
公衆送信権とは何か?
公衆送信権とは、今年の4月28日から施行されたものです。もともとテレビやラジオを使って著作物を含むものを皆に流すことを定めた法律です。
”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物を有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。
実演家・レコード製作者には、自動公衆送信に関して公衆送信権は認められていないが、”送信可能化権”が認められている(著作権法92条の2)
※知的財産用語辞典より引用
オンライン授業が進んだことで、法的に整備されたことが背景にあります。
公衆送信権とは、「いろんなものをテレビ、ラジオ、インターネットを使って流してよい権利」と解釈できます。
もともと著作物を作った本人自身(ミュージシャンら)には、もともと公衆送信権を持っているけれど、著作物をもたない学生らが、インターネットを使ってそれらを流してよいのか?という問題があげられます。なので、著作物を持たない学生がオンラインで人の作った曲を流してよいのか?という議論が行われました。
[ad2]コロナ禍でオンライン授業がメインに!
近年、コロナ禍で学校の授業でオンライン授業がメインになりました。オンラインで授業に使う資料(著作物)インターネットで先生が生徒たちに配信しています。
もともと、授業などで著作物を送信するには、「SARTRAS」(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に補償金を納めればOKです。
それが、コロナ禍ではそうしなくて大丈夫になりました。2020年度だけは、補償金が「無償」です。2021年度も引き続き、この方針が継続されそうです。
ただし、この制度については、全校生徒または保護者だけの配信で、限定範囲内の場合です。このことが改正著作権法35条に明記されています。
[ad2]学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)にお
改正著作権法 第35条より引用「https://sartras.or.jp/より」
いて教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に
供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表
された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作
物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができ
る。
ミュージシャンの曲を演奏する文化祭、ダメなこと・良いこと
文化祭をYouTubeで配信するのは良い~例外あり~
YouTubeなどは、JASRACと楽曲の許諾契約を結んでいます。そのため、文化祭でミュージシャンの曲を演奏している動画をYouTubeにUPするのは大丈夫です。
JASRAC管理外の海外ミュージシャンの曲などはやめておいたほうがいいです。
文化祭の様子をCD、DVDにして配るのはダメ
ミュージシャンの曲を演奏したものを、勝手にCDやDVDにするのはダメです。ミュージシャンの曲には、著作権だけでなく著作隣接権など別のものがあるためです。
まとめ・オンライン文化際で著作権について学べる
学生たちが、コロナ禍の中、せめて楽しく文化祭をしたい、オンラインでやろうぜ!と盛り上がるのとっても良いと感じます。新しいアイデアと新しい何かが生まれそうな感じがします。
学生たちのオンライン文化祭、というアイデアのおかげで著作権について学ぶ機会を得ることができました。
ネット時代の公衆送信権。この権利の行使についてもっと調べてみます。