「13歳からのスマホルール」・導入部分から共感
「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」は、「はじめに」の部分から共感が湧き出ています。
スマートフォンやインターネットは「車」と似ています。きちんとマナーを守って運転を行えば、遠くまですぐに移動できる便利な相棒になる。小中学生の場合はスマートフォンやインターネットをどんどん使い始め、アクセル全開でかっ飛ばしているイメージです。「ぶれーきの踏み方」を伝えるようにしています。
「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」より引用
そうそう、スマホやネットは自分の知らない世界をどんどん教えてくれる便利な道具です。そこには危険がいっぱいです。その危険に気が付く力、おかしいぞ、と疑う力をつけるための知識、ノウハウがこの本には詰まっています。
「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」。子どもだけでなく大人も読みたい1冊です。
「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」がおすすめの理由
具体的でわかりやすい
「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」は5つの章から成り立っています。そのどれをとっても具体的でわかりやすいです。ニュースで事件として取り上げられたものを例に挙げているものも多く、ああぁ、そうだった、そうだった、そんなことあったな、と思いながら読み進めることができます。
そしてこの本、1番大切だな、と感じるのは、第1章です。
ネットの情報を疑おう
1章はネットの情報が正しいものかどうかいつも疑うこと、発信者が正しい所かどうか見極めることを書いています。これ、ほんとネットとかスマホを扱うときに一番大事です。
情報を鵜呑みにしない。情報源はどこか。情報を正しいものだと調べる力を身につけることが大切だとわかります。

子どもに教えたいことがさっそく出てきましたよ
私刑・ネットリンチ・炎上、どうする?
2章では、「私刑」との付き合い方、ネットリンチや炎上についてどう向き合うかが主に書かれています。私刑を行う人は、正義感に燃えてネットに書き込みしていくため判断力がかけていき、どんどんエスカレートしていきます。強い正義感が被害者、加害者をうむことにつながることを書いています。
自分の正義に反する行為を正義感で制裁することが、正しいのか?正義と戦う事でどんどんモンスターになっていることに気が付かせてくれる章です。
また、2章では、ソーシャルジャスティスウォーリアーという言葉の意味や、トーンポリングという言葉の意味も理解することができます。
SNSの危険性、ネットで商売、ソシャゲについても・・・。
その他、ネットに顔を出してしまうことの危険性、ネットで知り合った人と会う危険性、「ネットで稼ぐ!」などの情報がどういうものか、をわかりやすく説明しています。
他にもネットで稼ぐ事や、ソーシャルゲーム依存症についても書かれています。それぞれ本当の事、事実のみを書いているところに好感が持てます。
だめだ、やめろ、してはいけない、ではなくて事実を伝えてどう行動するかを考えさせる書き方です。
拡散希望・デマとの付き合い方
デマ情報と付き合う方法は、こつこつと注意して情報に飛びつかないこと、筋トレのようにデマに対する耐性をつけること、と本著では解説しています。
ほかにも告知、宣伝などの拡散希望、ペット・行方不明者探しの拡散希望、私刑としての拡散希望、と拡散希望に対する接し方も参考になります。
善意の拡散が、犯罪に加担する可能性があるという説明に納得です。ストーカーやDV被害など複雑な問題がありますので、ペット、人探しの拡散希望には善意だけで参加するのは問題があるよ、とわかりやすく書いてます。
まとめ・ネットは嘘ばかりだ、疑う力、正しい情報を得る力を
この本は、とてもわかりやすいです。まず冒頭で述べたようにネット、スマホを「車」と表現しているところから、とても共感が得られます。
危険だ、危ない、だからやめよう、という思考ではなく、危険だ、危ない、だからこそ安全な方法でしっかり使っていこう、という向き合い方に賛成です。
ネットやスマホで世界が広がるのは、とても素晴らしいことです。だからこそ情報の正確性をいつも追う力、調べる力をつけていく必要があります。
自分自身も、子どもたちにも、情報の正確性をつかむ力をつけて、自分と他の人の安全につながるようにしていきたいですね。


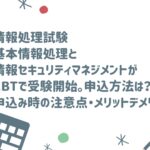

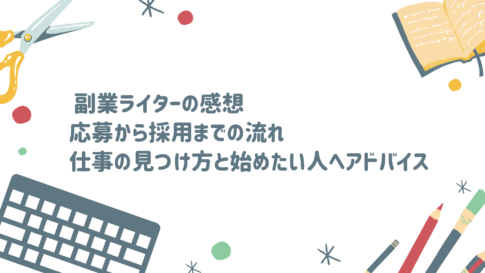


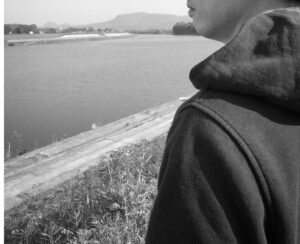
「ブレーキの踏み方」という表現に共感とすばらしさを感じました